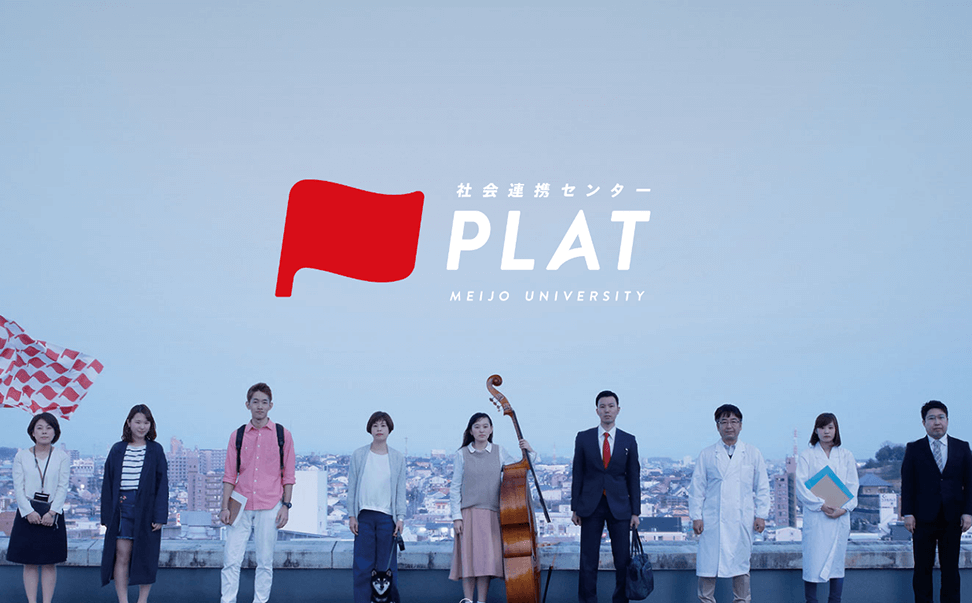特設サイト第124回 漢方処方解説(71)十味敗毒湯
今回ご紹介する処方は、十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)です。
この処方は、明代の「万病回春(まんびょうかいしゅん)」に収載された荊防敗毒散(けいぼうはいどくさん)をもとに、華岡青洲が改良した処方と言われています。荊防敗毒散は、癰(よう)、面疔(めんちょう)など皮膚の炎症疾患の一種で、感染が原因で発生することが多い疾患や背部の重篤な化膿症、乳腺炎などに用いたもので、防風、荊芥、羌活(きょうかつ)、独活(どっかつ)、柴胡、前胡(ぜんこ)、薄荷、連翹、桔梗、枳殻(きこく)、川芎、茯苓、金銀花(きんぎんか)、甘草、生姜の15種の生薬からなるもので、これを整理整頓し、いくつかの生薬を足したり、引いたりしながら、10味からなる十味敗毒湯としました。また、元々散剤でしたが、湯剤の方がより吸収性にすぐれ、効果の発現も早いとして煎じ薬としています。
構成生薬は、防風、荊芥、独活、柴胡、桔梗、川芎、茯苓、甘草、生姜、撲樕(ぼくそく)です。見慣れない生薬としては、独活があると思います。独活はウコギ科のウドの根茎を用いる生薬で、頭痛や関節痛などに対する鎮痛作用をもち、解熱や発汗、胃腸炎の改善に用いられます。羌活とともに基原植物に混乱のあった生薬ですが、羌活はセリ科のNotopterygium incisumやN. forbesiiの根茎及び根を用いる生薬で、医療用エキス製剤では独活の代わりに羌活を用いたものもあります。また、撲樕はブナ科のクヌギやコナラ、ミズナラ、アベマキの樹皮を用いる生薬ですが、バラ科ヤマザクラやカスミザクラの樹皮である桜皮(おうひ)で代用されることもあります。どちらも、鎮咳、収斂剤であり、瘡腫に用いるとされます。

独活(どっかつ)

撲樕(ぼくそく)
本処方は、化膿性腫物や膿瘍形成傾向のある皮膚の化膿性疾患に用いるもので、経験的にはじんましんや湿疹、乳腺炎、リンパ節炎などのほか、アトピー性皮膚炎や膿疱性ざ瘡などにも有用な場合があるとされています。もとになった荊防敗毒散しかりですが、感染性の皮膚疾患に用いられるものですし、抗菌薬の投与を考えたいような症状に応用できるという記述もあります。抗菌薬だけで完治しない場合とか、抗菌薬を使いにくいときには十味敗毒湯を使うという選択肢があるとされます。
エキス製剤がドラッグストアにも並んでいますし、化膿した湿疹や皮膚炎で悩むときには一助となると思います。
(2025年8月1日)