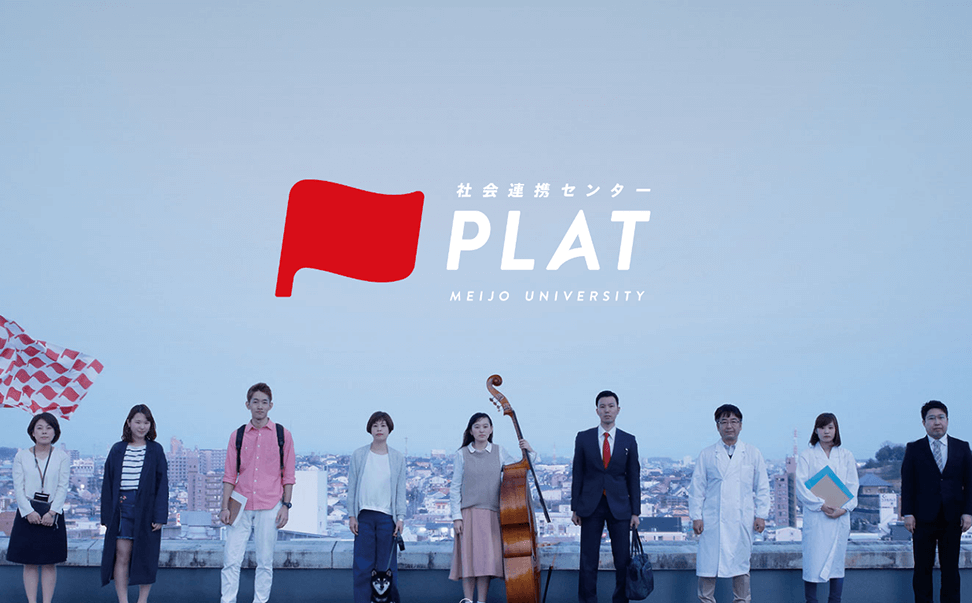<鼎談者紹介>
倉橋敏夫 氏 司法書士(倉橋敏夫司法書士事務所)
1974年 愛知県豊田市生まれ
1996年 慶應義塾大学法学部卒業
2004年 司法書士試験合格
2008年 倉橋敏夫司法書士事務所開業
2011年 名城大学法科大学院入学
2015年 同 修了(4年長期履修)、 同年司法試験合格
立岡 亘 教授
名城大学大学院法務研究科主任教授
弁護士(愛知県弁護士会、後藤?太田?立岡法律事務所)
実務家教員 (民事法総合演習 等担当)
梅津和宏 教授
名城大学大学院法務研究科広報委員長
元名古屋法務局長、大阪法務局長、旭川地?家裁所長、札幌地裁所長、東京高裁判事
実務家教員 (民事裁判演習 等担当)
鼎談
- 梅津 教授
- 今日はお忙しいところありがとうございます。「働きながら司法試験に挑む」シリーズの第二弾ということで、見事今年一発で司法試験に合格した倉橋敏夫さんをお迎えして、立岡先生を交えて、これから鼎談を開始させていただきます。名城大学は中京地区の法科大学院で唯一の昼夜開講制度をとっておりまして、これまでも多くの社会人の方が、仕事をしながら勉学を重ね、司法試験に挑んでまいりました。本日おいでいただきました倉橋さんも司法書士という仕事をされながら司法試験に合格されたのですが、その倉橋さんに、「司法書士の資格を有しながらさらに弁護士を目指したきっかけ」、あるいは「仕事をしながら勉強することのご苦労」、さらには「名城大学での学びの思い出」等々について、お話をお伺いしながら、現在社会人の方で法曹に興味を持っている方、法曹という夢を心に秘めている方、あるいは今現在本学で働きながら学んでいる学生諸君へメッセージをいただければと思って、この場を設けさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
それではまず最初に、先日、合格発表を聞いたときの気持ち、あるいは今現在の心境、というところからお伺いいたします。
- 倉橋 氏
- 合格したことは、この4年半、毎日勉強したことの成果ですから、自分がうれしいというのはもちろんありますが、それだけではなく、自分の周りの人が喜んでくれるので、二倍嬉しいというのがあります。その周りというのも、ロースクールの先生、支援員の先生であったり、同級生であったり、先輩、仕事で携わったことのある方や同じ司法書士の仲間が、私の予想以上に喜んでくれて、ご飯をご馳走してくださったり、とても毎日が新鮮で、幸せ感でいっぱいです。ありがたいことです。
- 梅津 教授
- 当然ながら、ご家族の喜びは人一倍だったと思うのですが。
- 倉橋 氏
- 妻も喜び、妻の実家も喜び、私の親も喜び、私の実家は豊田市の郊外にありまして、田んぼが広がる場所にあるのですが、地域の人から「うちのまちから弁護士さんが出るぞ」といってくれたりして、もちろん言いふらしてはないのですが、風聞が広がって地域の人にも喜んでいただいているようです。その意味では、やはり司法試験というのは特別なのかなぁと思っています。身が引き締まる思いもありまして、ありがたいことと思っています。
- 梅津 教授
- 合格されてから若干の時間が経過したのですが、心境の変化はありましたか。
- 倉橋 氏
- 受験勉強を毎日やっていたという状況から、今度は司法修習に向かうことになるのですが、今まで毎日やっていた勉強を急にやめるのはやはり違和感があって、なにかしら六法を引いたり、違う観点で司法試験の過去問を見たり、あとは、今年の司法試験について他の方が書いた答案を添削しながら俯瞰的に見てこうしたらよかったのかなぁなど考えたり、なんだかんだいって勉強をしているような感じです。あまり勉強以外をするということはない状況です。あと、弁護士の諸先輩方に食事につれていってもらったのですが、受験の情報ではなく、弁護士の情報を聞くことができるのは楽しいです。
- 梅津 教授
- 正直言って驚いています。試験に受かったら、「やった」と思って、あとは試験のことはしばらく忘れて、というようになった思い出があるのですが。立岡先生はどうでしたか。
- 立岡 教授
- 僕は、勉強不足でしたので、逆に言うと修習に入る前に何とかみんなに追いつこうと思って、それこそやってない勉強をしていたように思います。
- 梅津 教授
- そうですか。私が異質なようですから、次のテーマに移ります(笑)。
司法書士の仕事
- 梅津 教授
- 先ほどもご紹介させていただいたように、倉橋さんは司法書士のお仕事をされていらっしゃいます。司法書士の仕事として、具体的にどんな内容のお仕事をされていたのでしょうか。
- 倉橋 氏
- 一般に、不動産登記、商業登記それから債務整理をはじめとする簡易裁判所の管轄権の範囲内での代理権というのがあるのですが、私の仕事というのは、柱としては住宅ローンの抵当権設定であるとか、売買に伴う所有権移転等の登記手続が半分です。残り半分が、債務整理をはじめとする簡裁代理権の仕事でした。
- 立岡 教授
- 具体的な法廷活動もされたのですか。
- 倉橋 氏
- そうですね。過払金の返還は、ある一時期多かったというのはあります。ただ、140万円という制約の中ではありますが。
- 立岡 教授
- 証人尋問とか実際にされたのですか。
- 倉橋 氏
- 全くなかったです。
- 立岡 教授
- それは残念でしたね。
司法試験を目指したきっかけ
- 梅津 教授
- 不動産登記、商業登記もいわば法律に係わる仕事ですし、簡裁代理権もあったということなのですが、そのうえでさらに司法試験を受けようと思ったきっかけは何だったのですか。
- 倉橋 氏
- 2点あります。1つ目は仕事上の必要性です。つまり自分が食べていくための必要性です。2つ目はロマンです。
- 梅津 教授
- いいですねぇ。
- 倉橋 氏
- 1つ目の仕事の必要性といいますと、以前のまま司法書士という仕事だけを続けるとすると、まだ私は当時30代後半でしたので、あと30年、40年この仕事で食べていかなければならない。もちろん司法書士としての仕事の専門性を磨かないといけないのは当然なのですが、市場として、登記という分野が毎年縮小しているように感じます。弁護士はこのまま増える傾向にありますから、簡裁代理権があるといっても、そのマーケット自体も必ず縮小していくと思います。そうすると新たな能力といいますか、自らの専門分野を伸ばす、職域を増やすということが選択肢として必要であろうと思いました。例えば、相続登記の依頼を受けたとしても、そこで相続関係がまだもめているという場合は、司法書士ではどうやっても携わることはできませんから、弁護士さんにどうぞ、という形でお任せして、協議が終わった段階で登記をやりましょうねという話になります。それから、いくら相談にこられても、140万円におさまらないものであれば、ご相談自体を受けることができません。そういう仕事の必要性上、弁護士資格があれば、もっといろんなことができるであろうということと、私のところに来ていただいたお客さんのためにもいろいろな対応ができる、そういう必要です。
- 梅津 教授
- 簡裁代理権を得て、簡裁の仕事をしていたということが、むしろきっかけになったということもありましたか。
- 倉橋 氏
- そうですね。接点になりましたね。例えば、交通事故ひとつをみてもとても奥が深いものです。となると軽々に相談を受けるわけにもいきませんで、より深い知識が必要であろうということだとおもいます。
- 梅津 教授
- もう一つ。ロマンの方は。
- 倉橋 氏
- こちらは、私が学生の頃にさかのぼりますけれども、大学に合格して、豊田市から東京に出て行って、当時まだバブルの終わりかけの頃でして、ゴルフやスキーやテニスなどいろいろと遊んでました。したがいまして勉強しようなどとはぜんぜん思ってもいませんでした。ただ当時でも司法試験の予備校のパンフレットを抱えている同級生がいまして、「偉い子がいるなぁ」と思っていました。法学部に入って、「法曹の道に進む」というのはあるべき姿かなぁと思ってはいました。
その後、就職をして、司法書士にもなるのですが、法曹というのがずっと頭にあって、自然に検察官や弁護士が出てくるドラマを見ると、それがよみがえったりしていました。法律を駆使してそこで依頼人を救う姿にロマンを感じました。
- 立岡 教授
- 旧司法試験は考えなかったのですか。
- 倉橋 氏
- まったく考えませんでした。
- 立岡 教授
- そうしますと、ロースクール制度ができて、考え始めたということですか。
- 倉橋 氏
- そこは社会人の冷徹さ、といいますか、私も家庭がありますのでいろいろと考えます。一般に家庭を持っている方はそうでしょうけれども、ロマンだけでは食べていけないのですね。とすると、そこは考えます。司法試験は今どのくらいの合格率であるのか、とか、どのくらいのレベルにあるのか、など自分が受かる見込みを考えます。旧司法試験のころは、それがとても難しかった、というふうに自分で思っていた記憶があります。今どうなのかということをインターネットなどでしらべて、ある程度自分もチャンスがあるのではという見込みを確認して判断しました。
- 立岡 教授
- どこかの法科大学院に入らないといけない。ただ仕事をもっているので、夜の時間に授業をやっているとなると、名城大学というご判断をされたのですか。
- 倉橋 氏
- はい。私に仲の良い司法書士仲間がいまして、当時、その彼も名城大学に通っていましたので、内容の方も大体伺っていました。その意味で不安なく入学できました。
- 立岡 教授
- 名城大学に入る前の、そういうご友人の方のお話と、自分が実際に入学された後のイメージとでは違いなどありましたか。
- 倉橋 氏
- とても毎日が楽しかったです。まず、机に向かって勉強するという習慣がなかったものですから、あとは、視点が違うといいますか、われわれ毎日一問一答の世界で、勉強もしていたし、仕事もしていたような気がするのですが、「趣旨」、「原則」なんでしたっけ、という話をするのが、新鮮に感じました。不動産登記法の話をしても、その「背骨」の部分は民法の考え方だろうと思いますし、さらにその中には条文にない原理原則もあります。そういうところにさかのぼって考えるという思考回路が楽しかったです。友人知人ができたのももちろん良かったことです。
- 立岡 教授
- 倉橋さん、たしか長期履修でしたか?
- 倉橋 氏
- 4年にしてもらいました。
- 立岡 教授
- それは何かお考えがあってのことですか。
- 倉橋 氏
- 先ほどのお話をした友人も4年履修にしていて、「3年では難しい」という話も聞いていました。4年にして、準備を整えて一回で受かる、というのが自分に一番あっていると思いました。
- 立岡 教授
- それはご自分のライフスタイルや学力等を考えた結果として4年という期間を設定したのですか。
- 倉橋 氏
- はい。そうです。
入学後の勉強
- 立岡 教授
- さて入学後のお話ですが、入学されてみて実際に感じた負担感とか、そういう部分はいかがでしょうか。
- 倉橋 氏
- 予想していたよりは、やはり負担感はありました。特に予習復習の大切さという点でしょうか。まぁ予習復習が大切だとは聞いていましたけれども、それは予想を大きく上回っていました。予習3時間、復習3時間といわれますけれども、本当に分かろうとすると、その倍でも時間は足りませんし、そうすると要領というのが大事になってくると思います。
- 立岡 教授
- 今おっしゃられた予習復習の大事さというのは、たぶんこれからここで学ばれる人たちにとって重要なことだと思うのですが、倉橋さんの場合、予習?復習にどの程度時間をとられたのか、またその時に、自ら時間の枠のようなものを設けたのか、などに関して、どのような工夫をされたのでしょうか。
- 倉橋 氏
- やはり枠は設けました。それがないと際限なくやってしまいます。私は、予習と復習の比重を変えました。予習は最低限、大事なことは何か、程度にとどめて、復習の方を、むしろ予習の倍以上とるようにしました。それから復習もできるだけ目に焼き付けるといいますか、A4用紙一つ持ってきて、そこにマジックで、大事な言葉を書いて、その説明文を書くとか。あまり複雑なことは書かなくて単純な用語を書くとかして、それを実習室の自分のブースにはりつける。今日やったことは最低限これを覚えて帰る、ということをやっていました。その日、その科目で覚えたことを、一つでも持って帰る、理解を深めて帰る、という風でしょうか。
- 立岡 教授
- ご自分の勉強の方法を振り返ってみてどのように評価されますか。
- 倉橋 氏
- あまり手を広げすぎない。何が大切かについては必ず授業中に先生が言われますので、自分で線を引く。分からなければ聞けば何でも教えてくれますので、そこで聞いて確実なものにしておさえておく。それは最後で、迷ったときに「あのときの言葉」という形で、本試験の最中に浮かんできました。その積み重ねが役に立ちました。
- 立岡 教授
- お仕事もされながらということですが、勉強に当てる時間、授業に当てる時間の時間配分というのはどうでしたか。
- 倉橋 氏
- 最初のうちは、まず午前は仕事、午後はできるだけ早く学校へ行って勉強、仕事は学校が終わった後もう一度自分の事務所に戻って目を通してという生活をしていました。これが最初の二年です。ただ、できるだけ早く学校に行ってというのも、できる日とできない日がございます。完璧を求めるときりがないので、ここはある程度おおらかにみるといいますか、できなくてもそれはそれで受け入れるといいますか、やはり厳格さを求めすぎると、時に放り投げたくなってしまいますので。それは社会人ならではの考え方なのかもしれません。10できなくても、2、3はできるようにするという発想です。できないよりは少しでもできた方がまし、と考える。それは若い学生の皆さんとは違う考え方かもしれません。
- 立岡 教授
- 梅津先生もお勤めをしながら、受験勉強をされていたのでしたね。何か工夫されていたことはありましたか。
- 梅津 教授
- そうですね。やはり長丁場なので、結局のところ気力、体力との戦いのようなところがあるんですよね。その調整をどうされていたのか。例えば、僕は、土曜日の半分とか、日曜日の半分とかは絶対何もしないなど、いわば空白の時間を設けて、なるべく集中するようにしていたんですけれどもね。倉橋さんはそういう工夫はありますか。
- 倉橋 氏
- 日曜日は、全く勉強をしないことにしていました。もちろんやっている方もいらっしゃるのですが、私は、気力体力の充実のために日曜日を使っていました。
- 立岡 教授
- そうしますと、やはりメリハリをつけた勉強、それから意図的に勉強から離れる工夫も必要であるということですね。
それから先ほどのお話で、何か一つ今日の授業で得たことを持って帰る、という点については、私も全く同じことを言ってるんです。予習するときにはそういうことを意識して、分からないことをその先生にぶつけなさいと。そして終わった後でも「今日はあの先生こういうことを言っていたな」ということを思い出すだけでずいぶん違うということを言っています。でも、なかなか実践は難しいようですね。倉橋さんはその辺の意識がしっかりしていた、と思います。あと、先生の話だけではなくて、他の学生さんの質問やレポートも参考になった部分はありましたか。
- 倉橋 氏
- なりました。私とは違う視点が書かれてあったり、独学では分からないことがたくさんありました。
- 立岡 教授
- 人の意見を聞くこと。それを踏まえて批判することも大切な勉強方法だということでしょうね。
- 倉橋 氏
- 特に、私の場合は、松原さん(*H25本大学院修了、同年司法試験合格)、都築さん(*H26本大学院修了、同年司法試験合格)という良い見本がありましたから。勉強が進んだ人の見方というのはこういう視点なのか、というのが助かりました。

鼎談中の3人
授業と受験勉強とのバランス
- 立岡 教授
- 授業外に個別にゼミを組んだりすることはなったのですか。
- 倉橋 氏
- 私は他の曜日はできなかったのですが、土曜の夕方だけが空いていましたので、小山先生のゼミ(*若手弁護士による教育支援)には、二年生の終わりから、まる二年以上お世話になっています。そこではじめて、合格レベル、つまり完全な答案ではなくて「大事なレベルはこのレベル」というのを示していただきました。それで、書いてみようという動機も生まれました。最終的には合格レベルがここまで、というのを教えてもらいました。
- 梅津 教授
- もう少し、ゼミへの取組みを教えていただけますか。
- 倉橋 氏
- 小山先生のゼミだけしかとっておりません。小山ゼミは公法系以外の5科目を扱っていらっしゃいました。だからローテーションを組んでまずそれを一通り見ることができました。
- 梅津 教授
- そうですか。
- 倉橋 氏
- ただ、今年の司法試験で、私は公法系科目の出来が悪くて、受かったとは全く思っていませんでしたので、来年を目指してということで、司法試験後に、公法系のゼミに参加していました。
- 梅津 教授
- ゼミは当然司法試験を念頭においてのゼミということですよね。
- 倉橋 氏
- そうです。私は初めて司法試験の過去問を見たときに明らかに自分は対応できていないと思いました。それで答案をしっかり書かなければダメと思いましたし、せっかくゼミがあるのだからそれを活用しよう、ということです。まずはゼミに参加するという意思を固め、そして行く以上はなんか持って帰ろうということです。
- 梅津 教授
- 司法試験を意識するようになったのはいつごろからでしょうか。
- 倉橋 氏
- (4年間のうちの)3年生からです。だから半分過ぎたところからです。そこまでは、毎日、目の前のものを解決することに必死で、とてもじゃなかったです。
- 梅津 教授
- それはその頃には基礎が身についた、ということでしょうか。
- 倉橋 氏
- 基礎が身についたというのもあるのと、あとは、このくらいで意識しないと間に合わないだろうということです。これは先輩方から聞いていましたので。
- 梅津 教授
- 比率でいうと、授業と受験勉強とで、いつごろからどのような配分でやっていたのですか。
- 倉橋 氏
- 基本は半分半分だと思っていました。授業はもちろん一杯一杯でついていくのですけれども、その中でも試験対策というのを意識するようになりました。理想でいえば、半分の時間を費やしたいと思うのですが、なかなかそれはできなくて、できなくても必ず金曜日と土曜日だけは時間をとる、など、必ず受験勉強を頭の中においておくようにしました。その意味で、現実には受験勉強は最初は3割くらいだけだったように思います。
- 梅津 教授
- 逆に言うと、基礎的な部分が大切だということになりますか。
- 倉橋 氏
- 受験新報は3年目の後半くらいから約1年半くらいやりましたね。
- 梅津 教授
- 必ずしも割り切れるものではないとは思いますが、その司法試験対策というのと、授業の比重というのはどのくらいでありましたか。
- 倉橋 氏
- そうですね。授業としても、演習の問題そのものは大切ですが、その前に、その演習の問題の基礎は何か、何を聞いているのかを意識するようにしていました。演習問題の答えを暗記するのではなく、基礎があって、その例外の問題だったというような、位置づけなどを理解して帰るようにしていました。
- 立岡 教授
- 試験対策のことですが、択一式と論述式とありますが、そのあたりはどのような配分でしたか。
- 倉橋 氏
- 択一の問題は、問題集をやるという勉強方法でして、私は仕事場から大学まで、1時間半、通学の時間がかかります。往復、正味2時間電車に乗っています。この時間を全て択一に当てようという考えです。それだけでも毎日往復で20問解けますから、自然とそれで過去問を5周くらいは繰り返せました。それだけでした。解説読んで論文の勉強にもなりましたし。
- 立岡 教授
- そうしますとある面で、毎日2時間、択一問題のトレーニングをしていたということですね。
- 倉橋 氏
- それは、択一だけのために役立つのではなくて、必ず択一の問題にも重要な要素は含まれていますので、解説はむしろ読み物として読むことによって論述にもつなげられたかなと思っています。何もしないと電車の中で寝ちゃいますし。
- 梅津 教授
- ロースクール修了して授業がなくなった。その後の司法試験までの数ヶ月の勉強方法とか過ごし方とかはどうだったのでしょうか。
- 倉橋 氏
- まず、計画を練ることから始めまして、やはり、3、4ヶ月分の計画を立てるのですが、新しいことには手を出さない、という絶対のルールを立てました。これまでやったことだけ、今まである資料だけ、というルールを守ろうと。それで、4月に予備校の模試があります。それまでを一区切りと考えて、そこでできなかったことを全てはやらないで、もっとも点が伸びそうなところだけを攻略する。何か明確な指針を設けようとしました。それ以外のものは、割り切って捨てるということをしました。やはり完璧は無理です。それもゼミで学んだことです。
- 立岡 教授
- 模試等の経験を踏まえて、自分が想定していた点数と、現実の司法試験の結果との乖離みたいなものはありましたか。
- 倉橋 氏
- 本番では、あえて完璧は求めませんでして、落としてはいけない部分を落とさないように、ということでした。ある部分までできていて、これ以上できれば加点というところも教えてもらいました。それを踏まえて、まずは自分でここまで書ければ合格でしょう、という答案は作っていく。ゼミが終わったらその日のうちに修正して、自分なりの完全答案を作ってから帰るということをしました。
- 立岡 教授
- その完全答案を作り直してもう一度見てもらうんでしょうか。
- 倉橋 氏
- 見てもらったりもらわなかったりです。ただ、それがストックされて、各教科大体30~40通分くらいできるのですが、試験直前はそれしか見ていません。それが一番勉強になりました。
- 立岡 教授
- 宮島先生(*法務研究科教授)がいつもおっしゃっていることですが、添削してもらっても、もう一度完全なものとして作り直すという作業をやっている人が少ないとおっしゃっておられます。今おっしゃったように自分なりに書き直しをする、というのは、まさにその通りでして、感心しました。
- 倉橋 氏
- 早く帰りたいので終わったらすぐ作りました。
- 立岡 教授
- あと、苦手科目の克服はどのようにされていたのでしょうか。
- 倉橋 氏
- これは模試ではっきりと数字が出ていまして、民事系はそこそこ安定していました。ただ、刑事系が芳しくない。公法系はまずまず。なので刑事系と公法系をできるところだけやりました。とくに「刑訴の伝聞」と「憲法の作法」といった点が不安定なのがはっきりしましたので、残り一ヶ月の段階ですが、重点的に、そこに時間の半分を割いたりしました。
- 梅津 教授
- 試験の結果を先ほど伺ったら、弱いと思っていた部分がよくて、いいと思っていた部分はもう一つだったとか。
- 倉橋 氏
- そうなんです。試験は本当にいろいろなものが出てくるんだなあと思いました。思い込みではなく、客観的に自分をみて、そこにエネルギーを注ぐと、やればやるだけ結果が出ました。読んだ量より書いた量でした。
- 梅津 教授
- その辺を詳しく教えてもらえますか。
- 倉橋 氏
- 公法系は、独特な科目と思っていまして、「ちょっとだけやる」というのができない科目です。本当に完全答案を書こうとすると、丸一日かかってしまいました。この論点だけという書き方ができないものですから、どうしても足が遠ざかってしまう科目でした。その模試の際にそれを気づいて、もう一回過去問をやりなおしました。ただ公法系はいまいちでした。 刑事系は、まったく苦手だと思っていまして、私は学生時代勉強した覚えがなくって、先生の顔を思い出せないくらいなのですが、今回の試験では刑訴が一番得点をとることができました。油断をしないで原理原則をきちんと書こうと、そして苦手を素直に受け入れて、苦手な「伝聞」を一ヶ月猛特訓した結果だと思います。
- 梅津 教授
- その成果が出ましたね。
- 倉橋 氏
- おおらかにやれたのがよかったですね。大学の雰囲気も良かったですし、大体勉強計画なんかはうまくいかないのが当たり前で、それでもあまりあせらずにやらせていただいたのは良かったです。
- 立岡 教授
- そうやって大きな枠を作られて、その枠を自分なりに守って前に一歩一歩進んでいかれた計画性もお持ちだし、すごくバランスもいいなぁと思います。よくがんばられたと思います。現在受験勉強をしている方も、自分をしっかり見つめなおして、その上で枠をつくって、着実に実践して欲しいと思います。
家族の支え
- 立岡 教授
- ご家庭をお持ちだと聞きましたが、ご家庭とのバランスも大変ではなかったでしょうか。
- 倉橋 氏
- その点は、私の家族は理解があったといいますか、子供は確かに途中で生まれて、手はかかるんですけれども、負担よりも励みになった部分が強いです。子供の顔が活力のもとになりました。体力的、精神的な負担はあまりなくて、妻の実家も私の実家も両方すごく協力してくれましたし、ありがたかったです。
- 梅津 教授
- 在学中にビッグイベントがあったわけですよね。それはすごく大きなことだったと思うのですが。
- 倉橋 氏
- 私が唯一欠席した授業が、子供が生まれた日だけです。授業は全て出てるのですがその日だけです。
ロールクールでの日常生活

鼎談中の3人
- 立岡 教授
- ロースクールの日常において、楽しかったことあるいは逆につらかったことってありますか。
- 倉橋 氏
- あまりつらいということがなく、楽しいことばかりだったと思っています。なかなか社会人やってて、楽しいことの方が奇跡で、悔しいこととか、うまくいかないことの方がはるかに多いです。それに比べると、勉強して結果を出すというのが、面白くて。勉強さえすれば普通に結果は出ますし、そこが仕事とは違うんですよね。非常に分かりやすい世界ですし。
あとは、一回り以上年齢が下の子達と、一緒に勉強するというのは毎日楽しかったですね。非常に暖かく迎えてもらえて、一緒にご飯食べたり、ラーメン食べたり、お酒飲んだり。
- 立岡 教授
- 同級生とも、そういうように一緒に息抜きができていたんですね。これまでのお話を伺っていると、時間を上手に切り分けているというか、そういうのはお上手なように感じますね。すごいな、と思いますね。なかなかうまくいかない人もいるんですよね。勉強も中途半端、息抜きも中途半端、何かメリハリがないというか。その辺はどう思いましたか。
- 倉橋 氏
- この分野で大事なことは何かという意識をして、よく「幹をみろ」ということが本などに書いてあるのですが、細かいことばかりを追いかけるときりがないので、基礎中の基礎とは何かな、というような発想をすると、考える量も減るかなと思います。
今後のこと
- 梅津 教授
- それでは、今後のことをお聞きしたいと思うんですが。何か法曹としてやりたいと思うことはありますか。
- 倉橋 氏
- あまり大きな社会を変えるようなことは思わないのですが、今回の合格について、周りの方に喜んでもらえました。私なりにも人と人とのつながりというのがありますので、そういう人たちが何か困ったときに、頼りにしてもらえるといいますか、自分の生まれた豊田市でありますとか、仕事で携わることが多かった安城、岡崎のような地域で、いざというときに頼ってもらえる弁護士になれたらと思っています。
- 立岡 教授
- 弁護士以外の選択肢はないんですか。
- 倉橋 氏
- 全くありません。検察官や裁判官のドラマを見るのは好きですが。
- 立岡 教授
- バランス感覚も持っているし、いい検察官になるんじゃないのかなぁと思ったので。今のお話ですと、地域に根ざした弁護士になりたいということですね。
- 梅津 教授
- 立岡先生、その辺で倉橋さんにアドバイスありますか。
- 立岡 教授
- そうですね。法的な手続をとって救済の手助けをできるのは、私たち弁護士しかいません。そのために資格が与えられたわけですから、お金とか何とかいうのではなく、困っている人がいれば、そのために自分がいるんだ、という気持ちを常に忘れないことだと思います。僕らのときは、給費制でしたから、国からお給料をもらって勉強させてもらっていましたし、それなりに自由を謳歌させてもらったという恩義は感じていますが、今の人たちはそれがなくなって、全部自分でやらないといけないので、そのあたりが感覚的にずれがあるかもしれませんが。気持ちの上では、何のために資格が与えられているのか、ということを考えて、困っている人がいれば相手がどんな相手であろうとも闘う。みんなが投げ出した案件であっても助けなければいけない場合もある。そういう意味でも、資格を持った人間としての行動は大事だと思います。現実的には大変かもしれませんが、困っている人はいくらでもいますので助けてあげてください。
- 梅津 教授
- その辺は、倉橋さんどうですか。
- 倉橋 氏
- つい最近、司法書士として最後の仕事をしたんですが、農地の問題です。ある田んぼがAさん、Bさん、Cさんの共有状態にあって、Aさんがずっと管理しているので、Bさん、Cさんは別にその土地は要らないんです。でもそれを贈与とか売買というと、これは農地なので、農地法の許可によって縛られています。ただ、基本的には許可って難しいんですよね。でも、お客様はAさん単独所有を希望されています。そこで、持分放棄と言う法形式ですと農地法の規制が及ばないと考えました。これを法務局も認めてくれまして、その困った方が非常に喜んでくれました。これはロースクールの授業が役に立った例でして、農地法の趣旨とは何か、というのを考えると、意思を介した移転のみに規制が及ぶんですよね。だからどこに聞いてもダメと言われていたお客様の役に立てたというのは、私自身も嬉しい。こういう経験ができると言うのはいい仕事だなぁと思いました。
- 立岡 教授
- まさに知恵と工夫じゃないんですか。これはある面で法律家になられたときに、必要だと思うんですね。よく言われているのは法律家というのは好奇心の強い人が多いといわれていますね。好奇心が強いということは、それだけいろんな視点を持って、工夫をして、アプローチの仕方を変えていく。そういう意味ではそういうことができるというのはいいセンスを持っていますから、ぜひ生かしていただきたいと思います。
- 梅津 教授
- ロマンを実現できる立場に一歩進んだわけですけれども、どう具体的に結び付けていこうか想定されていますか。
- 倉橋 氏
- 今はあまり具体的なことを考えるよりも、いろいろな人の意見を聞いたり、これから修習にいったら、また違った意見を持った人にたくさん会えますので、だからあまり今はあまり具体化しないようにしています。その方が、楽しみが多くていいかなと思っています。
- 立岡 教授
- 修習時代にいろいろなところを見せてもらえますから是非ご覧になってください。裁判官や検察官も面白いぞとなるかもしれません。
- 梅津 教授
- そのついでに言わせていただくと、ものの見え方は立場によってぜんぜん違ってくると思うんですね。僕らのときにも言われましたが、弁護士になるのであれば、裁判官や検察官の世界を内部から見ることは今後はないわけで、そういう意味では、立場の違う人がどんな風に考えているのかということをじっくり見てきて欲しいですね。
社会人でありながら法曹を目指している方へ
- 梅津 教授
- それでは終わりも近づいてまいりましたが、今、社会人でいながら、法曹を目指している方たちがたくさんいると思うんですね。そういう方に対してのメッセージがあればお伝えいただければと思います。
- 倉橋 氏
- 法曹資格はいろいろなことが実現できる資格だと思っています。時代の変化は激しいもので、今ある仕事が10年後にあるか分からないし、働いている人は今の仕事で食べていけるのか不安に思うこともたくさんあると思います。法曹資格としても、今と常に同じ仕事ではなく、やれる仕事も変化していくと思います。社会の変化に対応していろいろな仕事ができる可能性をもった資格、それくらいの価値を持った資格だと思います。いざ合格してみると、いろいろな犠牲を払っただけの価値はあると思います。これは合格してみないと分からないのですが、ぜひともこの楽しさだとか、充実感であるとかを味わって欲しいです。
- 梅津 教授
- 大変貴重なお話をいただきました。それではありがとうございました。